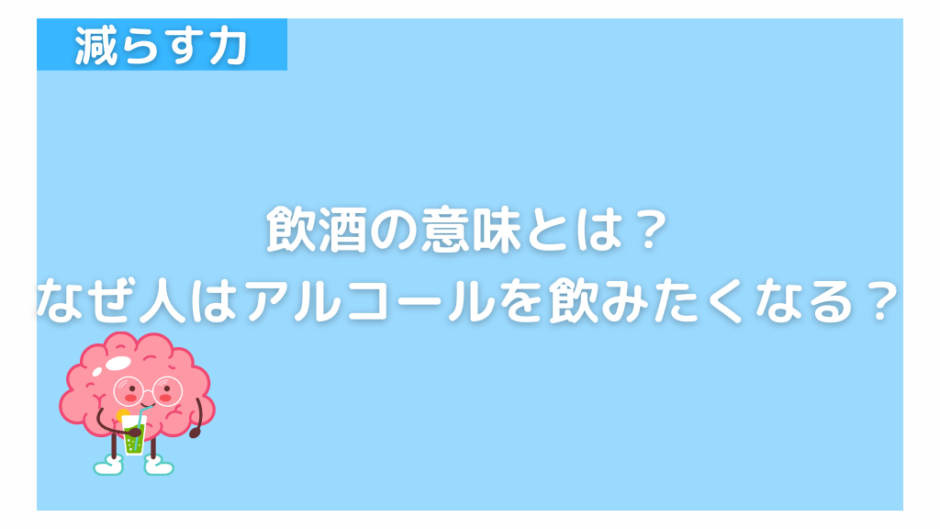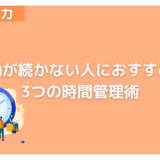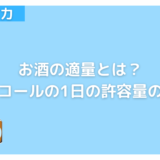こんにちは。
みちのくDr.です!
本日は、なぜ人はアルコールを飲みたくなるのか飲酒による影響いて紹介します。
お酒が好きで毎日飲む人も、アルコール飲料をあまり飲まない人も、
「どうして人はアルコールを飲みたくなるのだろう?」
「飲酒する意味とは?」
と考えたことありませんか?
なぜ多くの人がアルコールを飲みたいと思ってしまうのか不思議に感じる人は少なくありません。
そこで、本記事では、
- 飲酒について|脳や体への飲酒による2つの影響
- アルコールをさらに飲みたくなるのはドーパミンの影響
この2つをもとに、脳や体への飲酒による影響についてわかりやすく紹介します。
飲酒による影響を知って、どうしてお酒を飲んでしまうのかわかると、お酒を飲む量や機会を減らすのに役立てることができます。
ついお酒を飲んでしまうものの、自分の体の健康には気をつけたいを思う人は、なぜアルコールを摂取してしまうのかぜひ本記事で確認してみてください。

なんとなくお酒を飲みたいと思うことありませんか?自分もついお酒を飲みたいと思って飲んでしまうことがあります。
でも、なぜ人はお酒を飲みたいと思ってしまうのか不思議ですよね。
どうしてお酒を飲みたいと思ってしまうのか、以降で一緒に確認していきましょう!
目次

はじめに、飲酒による体や脳への影響について紹介します。
お酒を飲むと、胃や小腸で吸収されて血液に入り、全身にアルコールが行き渡ります。
アルコールは脳や神経に作用すると、次の2つの飲酒による影響が順番に出てきます!
- 脳や体を興奮させる
- 脳や体を落ち着かせる
お気づきの通り、上記の2つの作用は正反対のアルコールの効果です(1, 2, 3)!
では、具体的にはどのような影響が体に現れるのか、以降で詳しく説明します。
飲酒による影響①ドーパミンの影響で脳や体が興奮する
アルコールを飲んだ時に一番最初にでる飲酒の影響は、脳や体を興奮させる作用です。
アルコールを飲むと、一時的に快楽や幸せを感じさせるドーパミンというホルモンが出て、
- 幸福感
- 気分の高揚(こうよう)
- 血圧の上昇
- 心拍数の上昇
といった作用が体に出ます。
このような作用が出るドーパミンは、仕事や勉強などで成功した時に出るホルモンで、別名「快楽ホルモン」とも呼ばれるホルモンです。
誰しも人間の脳は、ドーパミンのホルモンの影響を受けたいと思って行動することがほとんどで、ドーパミンの影響で「お酒を飲みたい!」と判断するようになります。
このような効果はアルコールを含め、
- アルコール
- カフェイン
- ニコチン
などの成分に含まれるため、多くの人はお酒・エナジードリンクやコーヒー・タバコが欲しいと感じてしまいます(1, 2, 3)。
実は、このドーパミンの作用は覚醒剤などの効果とほとんど同じです。
しかし、ドーパミンによる効果は一時的なため、ドーパミンの効果が切れると次に紹介する効果が出てきます。
飲酒による影響②ドーパミンが減って脳や体が落ち着く
アルコールを飲んで少し時間が経過すると出てく飲酒の影響は、脳や体を落ち着かせる作用です。
先ほど説明したドーパミンの効果が切れてくると、脳や神経の興奮が落ち着いてきて、
- 血圧の低下
- 心拍数の低下
- 脳の機能の低下
などが出ます。
脳の機能が低下すると、ふわふわした気分になったり判断力が低下して、眠たくなります。
感のいい人はお気づきの通り、この作用は睡眠導入剤や鎮静剤とほとんど同じ作用です(2)。
そのため、眠れなくてお酒を飲みたくなってしまう人は、お酒を飲んで少し時間が経った後の飲酒による影響欲しさにアルコールを飲んでしまうことがあります。

お酒には「興奮」させる作用と「鎮静」させる作用の2つの影響があります。
すごく極端に言えば、飲酒は「覚醒剤」と「鎮静剤」の両方を同時に飲むことと同じです。
そう考えると、アルコールはなかなか体に良くないものだとわかりますよね。
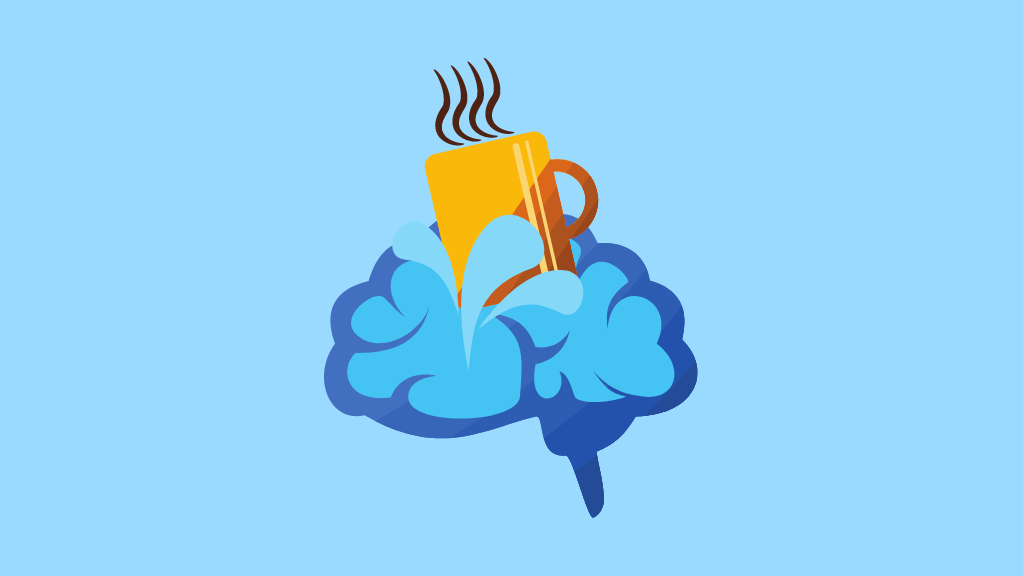
お酒を飲みたくなる理由がわかったものの、1杯で止まらず、2杯3杯とついついたくさん飲み過ぎてしまうのはどうしてか疑問に感じる人もいますよね。
ズバリ、アルコールをさらに飲みたくなってしまうのはドーパミンの効果がもっと欲しくなってしまうためです(3)。
先ほど紹介した脳や体への飲酒による2つの影響の中でも、実は興奮させる作用よりも落ち着かせる鎮静剤のような作用のほうが強いです。
興奮させる作用 < 落ち着かせる作用
そのため、アルコール飲んで時間が経過すると「もっと興奮した気分になりたい!」と感じて、さらに飲酒してしまいます。
そうして、気分がハイ→落ち着く→気分がハイ→落ち着く→…と、飲酒だけで完結する負の連鎖が始まって飲み過ぎてしまいます。
そのため、「1日1杯まで!」などと意識的に制限しないとどこまでもお酒を飲むことになってしまうので、お酒はあらかじめ量を決めて飲むことがおすすめです。

アルコールは1gあたり7キロカロリーで肥満などの生活習慣病はもちろん、脂肪肝などの肝臓の病気の原因にもなります。
また、筋肉もアルコールを代謝して分解しますが、同時に筋肉も分解されてしまいます。
お酒は飲み過ぎてもいいことは全くないので、お酒に飲み込まれないように上手にお付き合いすることがおすすめです!

本記事では、
- 飲酒について|脳や体への飲酒による2つの影響
- アルコールをさらに飲みたくなるのはドーパミンのため
この2つをもとに、脳や体への飲酒による影響について紹介しました。
脳や体への飲酒による影響は、次の2つが主な影響です。
- 脳や体を興奮させる
- 脳や体を落ち着かせる
上記の2つの影響の中でも、アルコールは脳や体を落ち着かせる影響のほうが強いため興奮させる作用欲しさにもっと飲みたいと人に思わせます。
そのため、お酒は事前に飲む量を決めて楽しむことがおすすめです。
アルコールに飲み込まれないように、スマートにお酒とお付き合いしてみてください!

それでは今日も、良い筋トレライフを!
出典